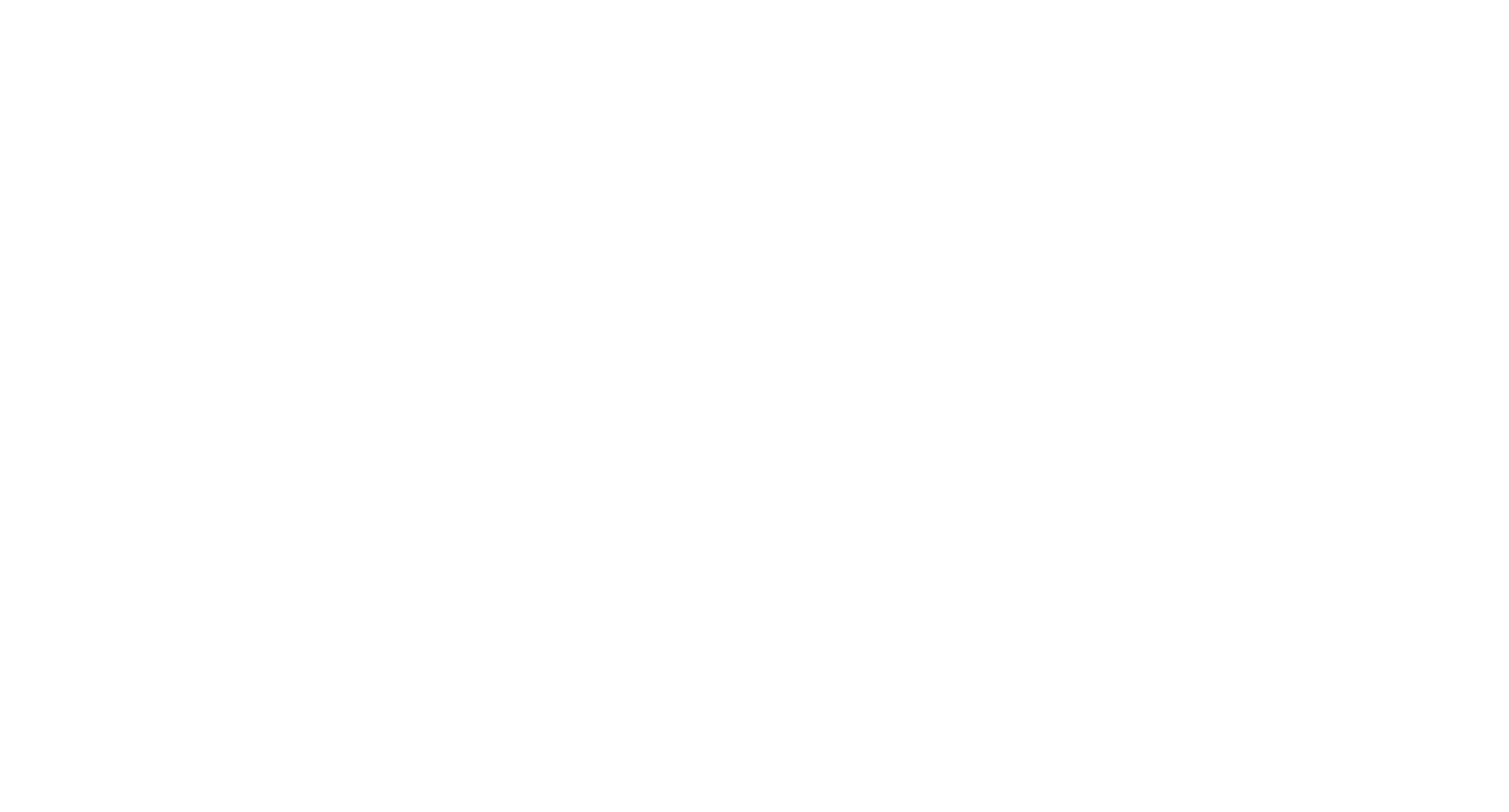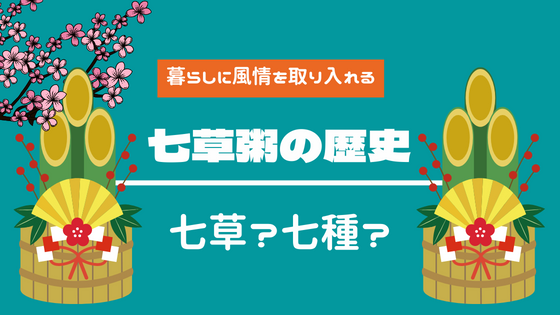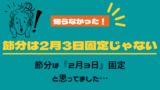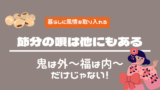1月7日に食べる七草粥。
七草粥を食べる由来は、諸説あるようですが、主な目的として『無病息災を願い食べる』のが七草粥。
現代では、お正月の三箇日に食べすぎた胃腸を休ませるという意味もあるそうです。
皆さんは、毎年、七草粥を食べる習慣はありますか?
私は約4年前から、日本の文化と風情をもっと大切にしようという思いで、七草粥を食べるようになりました。
七草粥の起源
平安時代には七草粥を食べる習慣があり、七草粥の起源は日本と思われるかもしれませんが、意外や意外、七草粥の起源は中国と言われています。
そして、当時は”七草”を食べていたわけではなく”七種粥”を食べていたそうです。
七草粥の風習は中国から伝わったものです。日本では平安時代の初期に宮中の行事となり、江戸時代になって庶民に広まりました。
引用:七草研究会、『七草粥の豆知識』より
しかし、古代の粥は「七種粥」と言われ、その材料は、「米・粟・きび・ひえ・みの・ごま・小豆」と、今とはまったく異なったものでした。今の7種類になったのは、鎌倉時代になってからだと言われています。

七草粥の前身があったことに驚き!
そして、七草粥の前身は『七種粥』だったとは!1つ勉強になりました!
「七種粥」から現在の「七草粥」になったのは鎌倉時代からのようですが、それでも非常に歴史古い文化であることは間違いないようです。
七草粥の種類と、七草粥の唄
皆さんは、七草粥の種類を全て覚えていますか?
\七草粥に入れる7種の草はコチラ/
- セリ
- ナズナ
- ゴギョウ
- ハコベラ
- ホトケノザ
- スズナ
- スズシロ

七草の名前を覚えるのが難しい(汗)
七草粥に入れる7つの草の種類を覚えるための唄を子どもの時に習ったという方もらっしゃるのではないでしょうか。
こちらは現代に作られた歌のようですが、七草研究会によると、『七草囃子』という七草粥を作る時に歌う唄というものがあるそうです。
また、七草研究会によると「七草粥」は前日の夜に作るものだそう(下記引用参照)。
そして、まな板や包丁などを使って叩き拍子をとりながら、『七草囃子』を歌いながら粥を作っていたそうです。
昔、七草粥を作るときは、七草を刻みながら歌をうたいました。この歌を七草囃子と呼びますが、今では知る人も少なくなりました。
一般的には、次のようなものだとされています。
引用:七草研究会、『七草粥の豆知識』より
七草粥は、古来の風習では6日の夜から作り始めます。まず、七草のほかに、まな板・火箸・擂粉木(すりこぎ)・包丁・杓子(しゃくし)・薪・菜箸を用意します。そして包丁や擂粉木でまな板を叩き拍子を取りながら、「七草なずな、唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に…」という言葉を6日の夜に28回、7日の朝には21回唱えます。
七草囃子はYoutubeでも聴けるので、今年は昔ながらの『七草囃子』を覚え、日本の歴史を感じながら、七草粥を作ってみたいと思います。
ぜひ皆さまも、1月7日は七草粥を食べて、日本の風情を感じながら、無病息災をお祈りしませんか?
\日本の文化、風情を楽しむ暮らし/